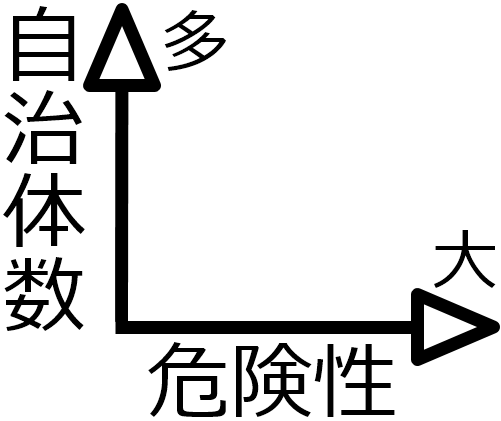小林市防災マップ推進事業とは
【事業概要】
小林市では、「協働により九州一安心安全なまち小林市」を実現するため、様々な事業を行っています。
その具体的活動として、国立研究開発法人防災科学技術研究所が開発・研究している「eコミプラットフォーム」を活用した防災マップの作成を推進しています。
地域等でマップを作成していく過程を通じて、住民の皆さんの防災意識の高まりや地域の防災力の向上を目指しています。また、災害等発生時における実質的な避難・減災行動につながることを期待しています。
【事業対象】
主に自主防災組織等(自治会区や地域集落等)
e防災マップ
お知らせ
情報検索・推奨検索機能
あなたの地域を知ろう
現在、他の地域 の情報を見ています。
-
自然特性
あなたの地域の自然特性を以下のように推定しました。
沿岸地域 津波による浸水被害が起こりうる地域
海岸線から3km以内の面積を集計し、自治体面積に占める割合を算出
出典:国土数値情報 行政区域データをもとに海岸線からの3kmのバッファ距離を持つポリゴンデータを作成埋立・干拓地 地震の揺れによる液状化が起こりうる地域
微地形区分図をもとに「干拓地」「埋立地」に該当するメッシュの総メッシュ数を集計し、自治体面積に占める割合を算出
出典:若松加寿江・松岡昌志・久保純子・長谷川浩一・杉浦正美(2004)「日本全国地形・地盤分類メッシュマップの構築」土木学会論文集 No.759/I-67,213-232.
河川・湖沼・ため池 浸水の被害が起こりうる地域
出典:河川は国土数値情報 河川データ、湖沼・ため池は国土数値情報 湖沼データをもとにメッシュにかかる総数を集計し、自治体面積(総メッシュ数)に占める割合を算出
平野部 河川の氾濫や、低地の浸水が起こりうる地域
微地形区分図をもとに「谷底低地」「扇状地」「自然堤防」「後背湿地」「旧河道」に該当するメッシュの総メッシュ数を集計し、自治体面積に占める割合を算出
出典:若松加寿江・松岡昌志・久保純子・長谷川浩一・杉浦正美(2004)「日本全国地形・地盤分類メッシュマップの構築」土木学会論文集 No.759/I-67,213-232.丘陵地・台地 市街地等で土砂災害が起こりうる地域
微地形区分図をもとに「丘陵」「火山性丘陵」「岩石台地」「砂礫質台地」「ローム台地」に該当するメッシュの総メッシュ数を集計し、自治体面積に占める割合を算出
出典:若松加寿江・松岡昌志・久保純子・長谷川浩一・杉浦正美(2004)「日本全国地形・地盤分類メッシュマップの構築」土木学会論文集 No.759/I-67,213-232.山地 土砂災害や地すべり等の災害が起こりうる地域
微地形区分図をもとに「山地」「山麓地」「火山地」「火山山麓地」に該当するメッシュの総メッシュ数を集計し、自治体面積に占める割合を算出
出典:若松加寿江・松岡昌志・久保純子・長谷川浩一・杉浦正美(2004)「日本全国地形・地盤分類メッシュマップの構築」土木学会論文集 No.759/I-67,213-232.火山地域 火山に起因する被害が起こりうる地域
微地形区分図をもとに「火山地」「火山山麓地」に該当するメッシュの総メッシュ数を集計し、自治体面積に占める割合を算出
出典:若松加寿江・松岡昌志・久保純子・長谷川浩一・杉浦正美(2004)「日本全国地形・地盤分類メッシュマップの構築」土木学会論文集 No.759/I-67,213-232.多雪地域 豪雪、風雪による災害が起こりうる地域
国土数値情報ダウンロードサービス・豪雪地帯(気象データ)から各年度別最深積雪(平均値)に基づいて内挿処理をした結果から、最新積雪が25cm以上のメッシュを抽出し自治体面積に占める割合を算出
出典:国土数値情報ダウンロードサービス・豪雪地帯(気象データ) 沿岸地域 埋立・干拓地 河川・湖沼ため池 平野部 丘陵地台地 山地 火山地域 多雪地域 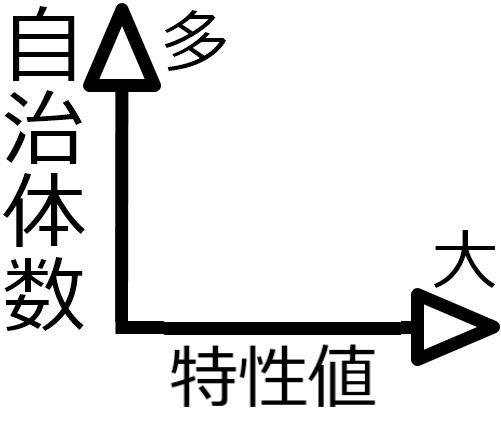
検索
-
社会特性(全国からみた 宮崎県小林市 の社会特性)
- 人口・世帯
- 出典:総務省統計局e-Stat(政府統計の総合窓口)「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(令和5年1月1日現在、2023年7月26日公表)
- 高齢化率
- 出典:総務省統計局e-Stat(政府統計の総合窓口)「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(令和5年1月1日現在、2023年7月26日公表)をもとに65歳以上人口の割合を計算
- 財政力指数
- 出典:総務省「令和4年度地方公共団体の主要財政指標一覧」
|
|
-
実態
左側表示年右側表示年
- 人口・世帯
- 出典:総務省統計局e-Stat(政府統計の総合窓口)「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(令和5年1月1日現在、2023年7月26日公表)
- 高齢化率
- 出典:総務省統計局e-Stat(政府統計の総合窓口)「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(令和5年1月1日現在、2023年7月26日公表)をもとに65歳以上人口の割合を計算
- 財政力指数
- 出典:総務省「令和4年度地方公共団体の主要財政指標一覧」
- 区分
- 出典:総務省「地方公共団体の区分」
- 面積
- 出典:国土数値情報 行政区域データ
-
人口:人人口(65歳以上):人世帯数:面積:km²※表示時少数第4位四捨五入
-
人口 高齢化率 財政力指数 区分 人口密度 世帯数 面積 43,554人 37.5% 0.38 市 77.0人/km² 22,195 565.690km²
| 災害 | 結果 | 指標 | データ | 検索 |
|---|---|---|---|---|
|
地震
|
22.1%
|
あなたの自治体における「30年以内に震度6弱の揺れに見舞われる確率」の最大値を5段階で表示
選択した自治体の範囲内における、確率論的地震動予測地図(2021年度版)の「30年以内に震度6弱の揺れに見舞われる確率」の最大値を抽出し、5段階で表示 原典:確率論的地震動予測値図(文部科学省地震調査研究推進本部) |
30年以内に震度6弱に見舞われる確率 | |
|
液状化
|
可能性大:0.0%
可能性中:2.8%
可能性小:0.0%
なし:97.2%
スコア:0.1
|
あなたの自治体における「液状化の可能性」を可能性大・中・小・なしの割合から算出し、5段階で表示
選択した自治体の範囲内における、微地形区分図の地形分類からみた「液状化可能性の判定基準」をもとに液状化の可能性大・中・小・なしのメッシュ数を集計して、それぞれの可能性の割合を算出し、可能性別に重みづけをして得点化し、5段階で表示 (液状化の可能性)=3×(可能性大の割合)+2×(可能性中の割合)+1×(可能性小の割合)+0×(可能性なしの割合) 原典:若松加寿江・久保純子・松岡昌志・長谷川浩一・杉浦正美(2005)「日本の地形・地盤デジタルマップ」東京大学出版会,p.55,表2.5. |
液状化の可能性 | |
|
津波
|
0.0%
|
あなたの自治体における「海岸沿いの地形」の割合を算出し、5段階で表示
選択した自治体の範囲内における、微地形区分図の凡例区分で海岸沿いの地形に相当する「三角州・海岸低地」「砂州・砂礫州」「砂丘」「砂州・砂丘間低地」「干拓地」「埋立地」「磯・岩礁」かつ海岸線から10km以内の総メッシュ数を集計し、自治体面積に占める割合を算出し、5段階で表示 原典:若松加寿江・松岡昌志・久保純子・長谷川浩一・杉浦正美(2004)「日本全国地形・地盤分類メッシュマップの構築」土木学会論文集 No.759/I-67,213-232. |
海岸沿いの地形 | |
|
火山
|
41.7%
|
あなたの自治体における「火山地形」の割合を算出し、5段階で表示
選択した自治体の範囲内における、微地形区分図の凡例区分で火山地形に相当する「火山地」「火山山麓地」「火山性丘陸」の総メッシュ数を集計し、自治体の総面積に占める割合を算出し、5段階で表示 原典:若松加寿江・松岡昌志・久保純子・長谷川浩一・杉浦正美(2004)「日本全国地形・地盤分類メッシュマップの構築」土木学会論文集 No.759/I-67,213-232. |
火山に関する地形 | |
|
洪水
|
スコア:0.0
|
あなたの自治体における「浸水想定区域」の面積を浸水深に応じて得点化し、5段階で表示
選択した自治体の範囲内における、国土数値情報・浸水想定区域データに示される浸水想定区域の面積を集計して、自治体の総面積に占める割合を算出し、それぞれの浸水深で算出された面積割合に重みづけをして得点化し、5段階で表示 (洪水の危険性)={5×(浸水深5.0m以上)+4×(浸水深2.0m以上~5.0m未満)+3×(浸水深1.0m以上~2.0m未満)+2×(浸水深0.5m以上~1.0m未満)+1×(浸水深0m以上~0.5m未満)}/自治体の総面積 原典:国土数値情報ダウンロードサービス・浸水想定区域 |
浸水想定区域 | |
|
内水
氾濫 |
危険大:0.0%
危険中:2.8%
危険小:3.0%
危険なし:94.2%
スコア:0.1
|
あなたの自治体における「内水氾濫の危険性」を危険性大・中・小・なしの割合から算出し、5段階表示
選択した自治体の範囲内における、微地形区分図をもとに作成した「洪水ハザードマップ」の危険性大・中・小・なしのメッシュ数を集計して、それぞれの危険性の割合を算出し、危険性ごとに重みづけをして得点化し、5段階で表示 (内水氾濫の危険性)=3×(危険性大の割合)+2×(危険性中の割合)+1×(危険性小の割合)+0×(危険性なしの割合) 原典:若松加寿江・久保純子・松岡昌志・長谷川浩一・杉浦正美(2005)「日本の地形・地盤デジタルマップ」東京大学出版会,p.38,表2.1. |
洪水による浸水のしやすさ | |
|
高潮
|
0.0%
|
あなたの自治体における「海岸沿いの地形」の割合を算出し、5段階で表示
基盤地図情報の数値標高モデルデータ(10mメッシュ)から海岸線から10㎞以内で標高5m以下の総メッシュ数を集計し、自治体面積に占める割合を算出し、5段階で表示 原典:若松加寿江・松岡昌志・久保純子・長谷川浩一・杉浦正美(2004)「日本全国地形・地盤分類メッシュマップの構築」土木学会論文集 No.759/I-67,213-232. 基盤地図情報ダウンロードサービスサイト・数値標高モデル |
海岸沿いの地形 | |
|
土砂
|
1.9%
|
あなたの自治体における「土砂災害警戒区域」の面積が自治体面積に占める割合を算出し、5段階で表示
選択した自治体の範囲内における、国土数値情報・土砂災害警戒区域データから「土砂災害警戒区域(指定済)」「土砂災害特別警戒区域(指定済)」「土砂災害警戒区域(指定前)」「土砂災害特別警戒区域(指定前)」の4つの危険区域面積を算出し、自治体面積に占める割合を算出し、5段階で表示 原典:国土数値情報ダウンロードサービス・土砂災害危険区域 |
土砂災害危険箇所 | |
|
豪雪
|
0cm
|
あなたの自治体における最深積雪(平均値)の値を算出し、5段階で表示
選択した自治体の範囲内における、国土数値情報ダウンロードサービス・豪雪地帯(気象データ)から各年度別最深積雪(平均値)に基づいて内挿処理をした結果の最大値を算出し、5段階で表示 原典:国土数値情報ダウンロードサービス・豪雪地帯(気象データ) |
最深積雪量 | |
|
|
(該当データなし) | |||
| # |
市区町村
|
スコア |
人口
出典:総務省統計局e-Stat(政府統計の総合窓口)「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(平成29年1月1日現在、2017年7月5日公表) |
高齢化率
出典:総務省統計局e-Stat(政府統計の総合窓口)「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(平成29年1月1日現在、2017年7月5日公表)をもとに65歳以上人口の割合を計算 |
財政力指数 |
自然特性
全国で整備された情報をもとに推定した自然特性について、あなたの地域と一致する自然特性の数を提示 ※ 類似スコアの算出に用いられる値(一致する特性数 / 基準市区町村の特性数)と、一覧内の表示(一致する特性数 / 比較対象市区町村の特性数)は異なりますのでご注意ください。 |
社会特性
全国で整備された情報をもとに推定した社会特性について、あなたの地域と一致する社会特性の数を提示 ※ 類似スコアの算出に用いられる値(一致する特性数 / 基準市区町村の特性数)と、一覧内の表示(一致する特性数 / 比較対象市区町村の特性数)は異なりますのでご注意ください。 |
災害の危険性
全国で整備された情報をもとに推定した災害の危険性について、あなたの地域との一致率を提示 |
アカウント
地域防災Webサービスにおける類似の市区町村のアカウントの有無を提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
宮崎県小林市
|
- | 43,554人 | 37.5% | 0.38 |
5
|
2
|
- | - |
| 1 |
島根県 浜田市
|
1.01 | 50,681人 | 37.6% | 0.38 |
4/7
|
2/4
|
78.0% | |
| 2 |
岡山県 井原市
|
1.05 | 38,064人 | 37.6% | 0.4 |
4/4
|
2/3
|
84.0% | |
| 3 |
香川県 さぬき市
|
1.05 | 45,822人 | 38.0% | 0.39 |
4/6
|
2/4
|
76.5% | |
| 4 |
愛媛県 大洲市
|
1.32 | 40,580人 | 37.4% | 0.35 |
4/6
|
2/4
|
77.0% | |
| 5 |
徳島県 吉野川市
|
1.38 | 38,872人 | 38.1% | 0.36 |
4/4
|
2/4
|
74.9% | |
| 6 |
兵庫県 淡路市
|
1.42 | 42,437人 | 38.0% | 0.35 |
4/6
|
2/4
|
77.4% |
|
| 7 |
島根県 安来市
|
1.45 | 36,391人 | 37.5% | 0.35 |
5/7
|
2/4
|
77.7% | |
| 8 |
福島県 喜多方市
|
1.51 | 45,078人 | 36.7% | 0.37 |
5/6
|
2/3
|
64.5% | |
| 9 |
福島県 田村市
|
1.63 | 34,264人 | 37.0% | 0.35 |
4/5
|
2/3
|
86.0% | |
| 10 |
徳島県 阿波市
|
1.68 | 35,315人 | 38.0% | 0.35 |
4/4
|
2/3
|
75.5% | |
- ひなぎく
-
検索件数:0件
資料種別 タイトル 作成者 出版者・公開者 作成日 出版・公開年月日 提供元サイト
| キーワード | |
| 日付 | // - // |
| 資料種別 |
- TEAM防災ジャパン 防災人材情報
-
検索件数:件
写真 名前 肩書 所属 テーマ 詳細
関連タグ
関連した記事
| フリーワード | |
| タグ(キーワード) |
()
()
()
|